『僕の初恋ですか? ふふ、ファンの皆さんに決まってるじゃないですか』
テレビの中で英智くんが微笑むと、客席からキャーと黄色い声が上がる。それにすかさず『さすがやな、英智君!』なんてMCのお笑い芸人がツッコむと、スタジオの空気が一気に和やかになった。
そんな様子を、隣に座っている英智くん――本物の英智くんは、普段テレビを観るときと全く同じ、まるで他人事のような顔で眺めている。
そんな彼のもっと奥の顔を知りたくて、私は隣でソファに腰掛けている英智くんにひとつの疑問をぶつけてみた。
「ねぇ、英智くんの本当の初恋の人ってどんな人だったの?」
英智くんは私の言葉を聞くと、テレビの中で見せていたものと全く同じ笑みを私に返してきた。……この顔、きっと素直に話す気は無いんだろうな。彼は小さく首を傾げると、逆に私に問いかけてくる。
「そうだね……誰だと思う? 当ててごらん」
そう言うと彼は、ふっとその青い瞳を私に向けた。遠いものも近いものも透かしてしまうような、透明な青い瞳で。逆にこちらの心の奥を覗かれるような気がして、思わず息を呑んだ。
とはいえ、そんな昔のことなんて分かるわけない。初恋をするような年頃に私達はまだ知り合っていなかったから、見当も付かないのだ。とりあえずベタなところからかな。
「えー……そうだな、幼稚園の頃のクラスメイトとか?」
「ううん。そもそも僕はその頃からずっと病院にいたから、クラスメイトなんていなかった」
「ええー、じゃあ看護師さんとか……?」
看護師さんでもなかったらちょっとネタ切れかもしれないな。苦し紛れに口に出すと、英智くんは私と目を合わせたまま、はっきりと答えた。
「違う。僕の初恋は君だ」
「そんなわけ……」
――そんなわけない。英智くんの瞳は真剣そのものだったけど、にわかには信じがたかった。
英智くんと私が出会ったのは、少なくとも大人になってから――お互い、初恋の年頃なんてとっくに過ぎているはずの年齢だ。
目を逸らさずに向き合ってくる英智くんの瞳がなんだか気恥ずかしくて、思わず目を逸らす。すると、英智くんもソファに軽く背を預けて、身を引いた。
「逆に聞こうか。じゃあ、君の初恋は?」
「えっ」
思わぬ質問に間の抜けた声を上げてしまった。
私の初恋。それは紛れもなく、英智くんだ。
一目惚れだったのだ。彼を初めて見たのは私が中学生のとき――英智くんがまだ夢ノ咲にいた頃だ。話題急上昇中の高校生アイドルユニット――なんてコピーで売り出されていた『fine』。別にアイドルオタクとかではなかったけれど、たまたまfineが出ている番組を観た私は度肝を抜かれた。
センターで歌ってるブロンドヘアの男の子。リーダーの天祥院英智くんと言うらしい。優雅な踊りに優しい歌声、そして上品な微笑み。
クラスの男子くらいしかまともに同年代の男の子を見たことがなかった私は、この世にこんなにきれいな男の子がいるんだってことをその時初めて知った。整った顔立ちで、けれどただのお人形のようではなく、彼はステージの上で楽しそうに舞っていたのだ。
fineが映っていたのはバラエティ番組の中、ほんの数分だけのひとときだけだったけど、私の世界にキラキラ輝く光が差したような気がした。目に飛び込んでくる世界に、英智くんという新しい色が増えた。
あの日から、私はずっと天祥院英智に恋をしている。だから、私の初恋は英智くんなのだ。
「……言わない」
「どうして?」
……でもこんなこと、英智くんには言えない。だって英智くんと初めて知り合った時から、自分が英智くんのファンであることはひた隠しにしてきたからだ。
アイドルを支える仕事がしてみたい。ステージから煌めきを放つ英智くんを見続けているうち、いつしかそう思うようになった。別に英智くんとお近づきになりたいとか、fineのメンバーと会ってみたいとか、そういう下心が――あったことは否定できないけれど、もちろんそれは主たる理由ではなかった。もっと多くの人にこの煌めきの虜になってほしい、ただそれだけだった。
しかし中学生の私に、『あなたは将来アイドルに携わる仕事をして、なぜか英智くんとお付き合いをしているよ』と伝えたら、どんな反応をするだろうか……きっと信じてもらえないだろうな。
だって私もどうして英智くんとお付き合いできているのか、未だに分かっていない節があるくらいだもん。
「恥ずかしいから。……っていうか英智くんもはぐらかしてるじゃん」
「はぐらかしてる? 僕が? ひどいなぁ、本当のことを言っているだけなのに。君も教えてくれないと不公平だと思うけど?」
さっきまで余裕を纏っていた彼の表情がほんの少し曇った。軽く睨むような目つきに変わって、私をじっと見つめてくる。私がここまで頑なに口を開かないのが気に入らないのだろう。もし私の初恋が英智くん以外の、たとえばそれこそクラスメイトの男の子とかだったりして、そんな話を聞いて面白いだろうかとちょっと思うけれど……。
「わ、わたしは……言わないっ!」
彼の視線にも屈せず私が押し通すと、英智くんはため息を吐いてソファから立ち上がった。細い体躯から伸びる影がゆっくりと揺れる。
「ふぅん。そうかい」
見上げた彼の口元が小さく歪んだ――それを見つけた瞬間、ソファに腰掛けていた私の体は押し倒され、あっという間に彼の腕に抑えつけられてしまった。細くてしなやかな彼の体が、意外なほどの力で私を拘束する。
「英智く――」
もしかして怒らせてしまっただろうか。どうしよう、そんな考えが脳裏をよぎった瞬間、彼の手が私の体にすばやく伸びてきた。英智くんの考えることがますます分からなくなって一瞬困惑したものの、そんな感情は予想の斜め上の方向で裏切られることになった。
「ひゃっ――あは、英智くん!」
私を押し倒した英智くんは、私の脇腹に手を伸ばしくすぐってきたのだ。さらさらとあばらを走る彼の指がくすぐったくてたまらない。体をよじって逃げようとするものの、彼のもう片方の腕が私を逃がしてくれなかった。
「あはは、だめ、英智くん!」
必死に止めようとしても、ついきゃははと子供みたいな笑い声を上げてしまう。最初は真顔だった英智くんもつられて面白くなってきたのか、段々彼の顔にも笑みが浮かんできていた。
「ひゃ、だめ、わかった、言うからやめて」
「!」
私の言葉で英智くんの指が離れていく。彼の指から解放された私は、やっと落ち着いて息ができるようになった。はあはあと息を整えたあと、体を起こしてソファの上に座り直す。英智くんの瞳が、じっと私の答えを待っていた。
「私の初恋は……英智くん。私が中学生の頃、英智くんを見たとき……一目惚れした。こんなふうに付き合えるなんて、思っても見なかったけど」
「……そうか」
言葉にするにつれて、なんだか気恥ずかしさで顔が熱くなる。もしかすると、英智くんは最初から全部分かっていたんじゃないか、そんな破れかぶれな気持ちもしてきて――つい、口にする。
「英智くんのことだから、どうせ私の初恋が英智くんだってことも分かってたでしょ?」
「うん。君の言う通り、最初から君が僕のことを好いてくれていたのは気付いていた。まあ正直に言えば、君から言ってほしかっただけだね」
「最初から⁉ 最初……って、どこから?」
聞き捨てならない言葉につい声を大きくする。最初からって言ったら、まさか知り合った時にはもう彼のことが好きだということがバレていたのか。不安な気持ちで尋ねた私を半ばからかうように、彼は楽し気に語り始めた。
「最初は最初だよ。僕と君が初めて会ったときから。君は隠しているつもりだったみたいだけど、君の純粋な瞳はアイドルのファンのそれだった。分かるに決まってるじゃないか」
やっぱり。しかし、まさか最初からバレていたなんて――というか最初からバレていたなら、今までの私の努力は一体何だったのだろう……。落ち込むようにがっくりと肩を落とした私を覗き込むように、英智くんが視線を合わせてくる。
「だけど……やっぱり僕の初恋は君なんだなぁ、とも思ったかな」
「!――」
私の髪越しにはにかむような笑みを見せる英智くん。いつもは自信に満ちた笑顔を見せるのに、その時ばかりは英智くんがお年頃の男の子のように見えたのだ。とってもレアな彼の表情を前に、私は彼の言葉を信じざるを得なくなってしまった。
「英智くん」
「なんだい?」
「好き」
「ふふ。僕も好きだ。ずっとね」
そう言って額に小さなキスを落としてくれたお礼に、彼をぎゅっと抱きしめ返す――この幸せな気持ちごと抱きかかえるようにして。そうしてその夜は、ずっと彼のサボンの香りに包まれていた。
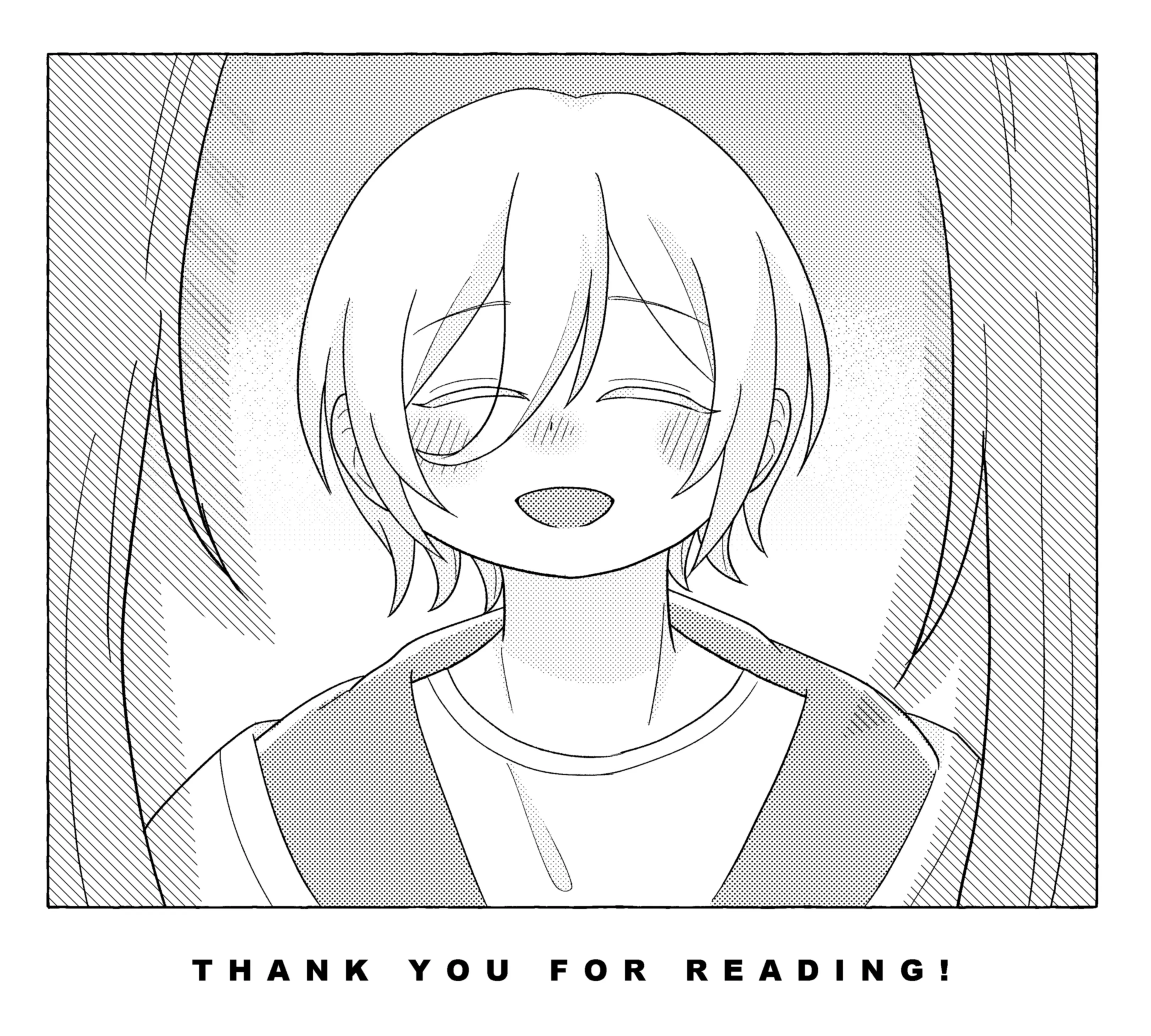
テレビの中で英智くんが微笑むと、客席からキャーと黄色い声が上がる。それにすかさず『さすがやな、英智君!』なんてMCのお笑い芸人がツッコむと、スタジオの空気が一気に和やかになった。
そんな様子を、隣に座っている英智くん――本物の英智くんは、普段テレビを観るときと全く同じ、まるで他人事のような顔で眺めている。
そんな彼のもっと奥の顔を知りたくて、私は隣でソファに腰掛けている英智くんにひとつの疑問をぶつけてみた。
「ねぇ、英智くんの本当の初恋の人ってどんな人だったの?」
英智くんは私の言葉を聞くと、テレビの中で見せていたものと全く同じ笑みを私に返してきた。……この顔、きっと素直に話す気は無いんだろうな。彼は小さく首を傾げると、逆に私に問いかけてくる。
「そうだね……誰だと思う? 当ててごらん」
そう言うと彼は、ふっとその青い瞳を私に向けた。遠いものも近いものも透かしてしまうような、透明な青い瞳で。逆にこちらの心の奥を覗かれるような気がして、思わず息を呑んだ。
とはいえ、そんな昔のことなんて分かるわけない。初恋をするような年頃に私達はまだ知り合っていなかったから、見当も付かないのだ。とりあえずベタなところからかな。
「えー……そうだな、幼稚園の頃のクラスメイトとか?」
「ううん。そもそも僕はその頃からずっと病院にいたから、クラスメイトなんていなかった」
「ええー、じゃあ看護師さんとか……?」
看護師さんでもなかったらちょっとネタ切れかもしれないな。苦し紛れに口に出すと、英智くんは私と目を合わせたまま、はっきりと答えた。
「違う。僕の初恋は君だ」
「そんなわけ……」
――そんなわけない。英智くんの瞳は真剣そのものだったけど、にわかには信じがたかった。
英智くんと私が出会ったのは、少なくとも大人になってから――お互い、初恋の年頃なんてとっくに過ぎているはずの年齢だ。
目を逸らさずに向き合ってくる英智くんの瞳がなんだか気恥ずかしくて、思わず目を逸らす。すると、英智くんもソファに軽く背を預けて、身を引いた。
「逆に聞こうか。じゃあ、君の初恋は?」
「えっ」
思わぬ質問に間の抜けた声を上げてしまった。
私の初恋。それは紛れもなく、英智くんだ。
一目惚れだったのだ。彼を初めて見たのは私が中学生のとき――英智くんがまだ夢ノ咲にいた頃だ。話題急上昇中の高校生アイドルユニット――なんてコピーで売り出されていた『fine』。別にアイドルオタクとかではなかったけれど、たまたまfineが出ている番組を観た私は度肝を抜かれた。
センターで歌ってるブロンドヘアの男の子。リーダーの天祥院英智くんと言うらしい。優雅な踊りに優しい歌声、そして上品な微笑み。
クラスの男子くらいしかまともに同年代の男の子を見たことがなかった私は、この世にこんなにきれいな男の子がいるんだってことをその時初めて知った。整った顔立ちで、けれどただのお人形のようではなく、彼はステージの上で楽しそうに舞っていたのだ。
fineが映っていたのはバラエティ番組の中、ほんの数分だけのひとときだけだったけど、私の世界にキラキラ輝く光が差したような気がした。目に飛び込んでくる世界に、英智くんという新しい色が増えた。
あの日から、私はずっと天祥院英智に恋をしている。だから、私の初恋は英智くんなのだ。
「……言わない」
「どうして?」
……でもこんなこと、英智くんには言えない。だって英智くんと初めて知り合った時から、自分が英智くんのファンであることはひた隠しにしてきたからだ。
アイドルを支える仕事がしてみたい。ステージから煌めきを放つ英智くんを見続けているうち、いつしかそう思うようになった。別に英智くんとお近づきになりたいとか、fineのメンバーと会ってみたいとか、そういう下心が――あったことは否定できないけれど、もちろんそれは主たる理由ではなかった。もっと多くの人にこの煌めきの虜になってほしい、ただそれだけだった。
しかし中学生の私に、『あなたは将来アイドルに携わる仕事をして、なぜか英智くんとお付き合いをしているよ』と伝えたら、どんな反応をするだろうか……きっと信じてもらえないだろうな。
だって私もどうして英智くんとお付き合いできているのか、未だに分かっていない節があるくらいだもん。
「恥ずかしいから。……っていうか英智くんもはぐらかしてるじゃん」
「はぐらかしてる? 僕が? ひどいなぁ、本当のことを言っているだけなのに。君も教えてくれないと不公平だと思うけど?」
さっきまで余裕を纏っていた彼の表情がほんの少し曇った。軽く睨むような目つきに変わって、私をじっと見つめてくる。私がここまで頑なに口を開かないのが気に入らないのだろう。もし私の初恋が英智くん以外の、たとえばそれこそクラスメイトの男の子とかだったりして、そんな話を聞いて面白いだろうかとちょっと思うけれど……。
「わ、わたしは……言わないっ!」
彼の視線にも屈せず私が押し通すと、英智くんはため息を吐いてソファから立ち上がった。細い体躯から伸びる影がゆっくりと揺れる。
「ふぅん。そうかい」
見上げた彼の口元が小さく歪んだ――それを見つけた瞬間、ソファに腰掛けていた私の体は押し倒され、あっという間に彼の腕に抑えつけられてしまった。細くてしなやかな彼の体が、意外なほどの力で私を拘束する。
「英智く――」
もしかして怒らせてしまっただろうか。どうしよう、そんな考えが脳裏をよぎった瞬間、彼の手が私の体にすばやく伸びてきた。英智くんの考えることがますます分からなくなって一瞬困惑したものの、そんな感情は予想の斜め上の方向で裏切られることになった。
「ひゃっ――あは、英智くん!」
私を押し倒した英智くんは、私の脇腹に手を伸ばしくすぐってきたのだ。さらさらとあばらを走る彼の指がくすぐったくてたまらない。体をよじって逃げようとするものの、彼のもう片方の腕が私を逃がしてくれなかった。
「あはは、だめ、英智くん!」
必死に止めようとしても、ついきゃははと子供みたいな笑い声を上げてしまう。最初は真顔だった英智くんもつられて面白くなってきたのか、段々彼の顔にも笑みが浮かんできていた。
「ひゃ、だめ、わかった、言うからやめて」
「!」
私の言葉で英智くんの指が離れていく。彼の指から解放された私は、やっと落ち着いて息ができるようになった。はあはあと息を整えたあと、体を起こしてソファの上に座り直す。英智くんの瞳が、じっと私の答えを待っていた。
「私の初恋は……英智くん。私が中学生の頃、英智くんを見たとき……一目惚れした。こんなふうに付き合えるなんて、思っても見なかったけど」
「……そうか」
言葉にするにつれて、なんだか気恥ずかしさで顔が熱くなる。もしかすると、英智くんは最初から全部分かっていたんじゃないか、そんな破れかぶれな気持ちもしてきて――つい、口にする。
「英智くんのことだから、どうせ私の初恋が英智くんだってことも分かってたでしょ?」
「うん。君の言う通り、最初から君が僕のことを好いてくれていたのは気付いていた。まあ正直に言えば、君から言ってほしかっただけだね」
「最初から⁉ 最初……って、どこから?」
聞き捨てならない言葉につい声を大きくする。最初からって言ったら、まさか知り合った時にはもう彼のことが好きだということがバレていたのか。不安な気持ちで尋ねた私を半ばからかうように、彼は楽し気に語り始めた。
「最初は最初だよ。僕と君が初めて会ったときから。君は隠しているつもりだったみたいだけど、君の純粋な瞳はアイドルのファンのそれだった。分かるに決まってるじゃないか」
やっぱり。しかし、まさか最初からバレていたなんて――というか最初からバレていたなら、今までの私の努力は一体何だったのだろう……。落ち込むようにがっくりと肩を落とした私を覗き込むように、英智くんが視線を合わせてくる。
「だけど……やっぱり僕の初恋は君なんだなぁ、とも思ったかな」
「!――」
私の髪越しにはにかむような笑みを見せる英智くん。いつもは自信に満ちた笑顔を見せるのに、その時ばかりは英智くんがお年頃の男の子のように見えたのだ。とってもレアな彼の表情を前に、私は彼の言葉を信じざるを得なくなってしまった。
「英智くん」
「なんだい?」
「好き」
「ふふ。僕も好きだ。ずっとね」
そう言って額に小さなキスを落としてくれたお礼に、彼をぎゅっと抱きしめ返す――この幸せな気持ちごと抱きかかえるようにして。そうしてその夜は、ずっと彼のサボンの香りに包まれていた。
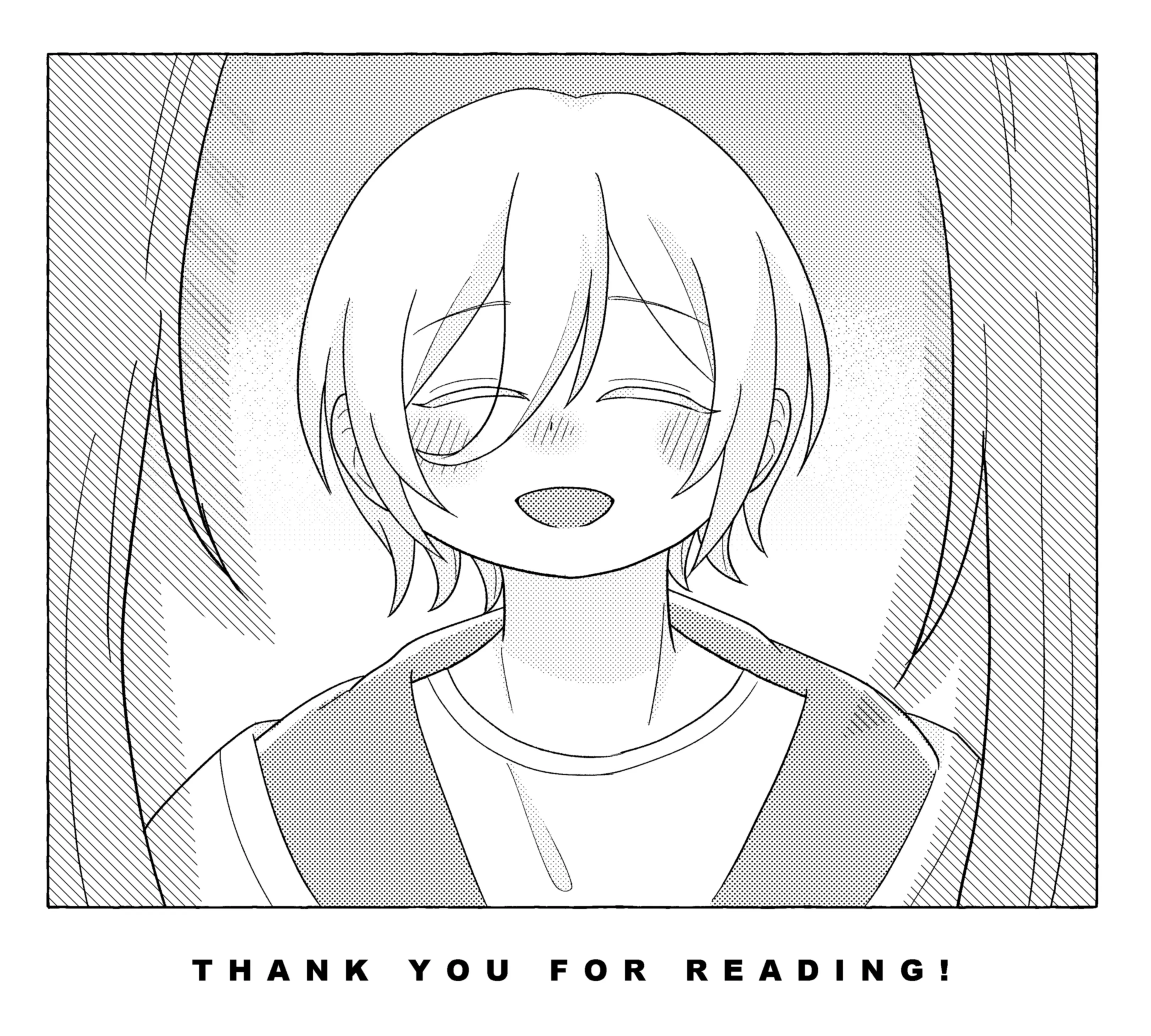
2025/05/25発行
夢道楽ペーパーアンソロジー企画参加作品